| ■市民研究宣言 Ⅲ 1997年2月1日 千里リサイクルプラザ研究所 機関紙『しみんけんきゅう』第3号 一昨年12月のはじめの一週問ほど、私はハワイの観光地、ホノルルにいました。でも目的は遊びと観光ではなく、日米リスク研究学会でもっぱらリスク・コミュニケーションの先端情報を集めることでした。 ■コミュニケーションとは? 阪神・淡路大震災での行政の対応はいうまでもなく、いじめと自殺にまつわる学校の対応にいたるまで、大小の組織の危機管理の弱さが政治・社会問題化してきました。 「リスク=危機」と翻訳するのは専門的にいうと問違いですが、ここではコミュニケーションに重点をおくので、リスクの内容には深入りしません。喉元すぎれば熱さを忘れたり、同じ日本といえども神戸の災害を対岸の火事視する東京に代表される、「日本人のリスク意識の低さ」という場合のリスクとして概念をつかんで下さい。 1984年(筑波)と1987年(吹田)の二度、日米のほぼ同じメンバーでリスク比較のワークショップが開かれた時、その頃まだ阪大にいた私が会の世話役を務めました。 84年にアメリカ側が提案した課題の大部分はリスクの分析や評価でしたが、87年には急にリスク・コミュニケーションの問題が取り上げられました。行政とボランティア市民の役割がうまく組織化されていて、災害時の対策も円滑に行われているアメリカからなぜリスク・コミュニケーション?、と私は一瞬わが耳を疑いました。 議論を通じて私が理解したのは、身近な自転車事故から人類の存続を脅かす核戦争にいたるまで、その発生確率や被害の評価、回避策などといった情報を徹底的に公開する必要性でした。 それから10年あまり経た今度の会議の初日、リスク・コミュニケーションのための公聴会の開き方の訓練コースを傍聴してやっと、私の理解がまだうわっすべりだったことがわかりました。 例えば、有害廃棄物の処分地の選定についての集会では、常にホットな議論が起こります。情報公開という面から見ると、なぜその場所が適地かということが問題の中心だと私は思っていました。 しかし、訓練コースを傍聴して理解できたのは、リスク・コミュニケーションの分野では情報公開の材料だけでなく、情報公開の手法についても神経を使うことが重要だということです。Q&Aの応酬の場で、一人ひとり知識も先入観も異なる市民を前にした行政側の説明者は、腕組みの善し悪しなどといったボディ・ランゲージの効果にまで習熟しておくべきだ、ということなのです。アメリカではそこまでリスク・コミュニケーションがマニュアル化されていたのです。 20年ほど前に、私は京都でアメリカ環境保護庁(USEPA)の市民対話の専門家の講演を聞いたことがあります。まだリスク・コミュニケーションという用語はなかったのですが、後年その人がエネルギー庁の原発立地問題の担当に転勤したというニュースが入りました。アメリカでは環境問題への市民参加の方が原発問題より先行していたともいえそうです。 日本の大学でも最近、人気のなかった教養課程を解体して国際関係学部などをつくる例が増え、ここには必ず「国際コミュニケーション学科」があります。でも、ここが単に英語教員のたまりになっているとも指捕されています。 英語で意見の交換や親密な交際をするという手法だけに頼って、ある共通の目的に向けて合意形成するような国際的な関係づけができなければ、コミュニケーションは成立しないはずです。  ワイキキのレストランで。ポリネシアン系に見えますか。 ■身のほど知らず? この第3号では「地震災害十リサイクル十ボランティア」を特集の課題にしました。 震災の現場やその後の復興の過程でこそ、日頃の市民研究の成果が発揮されるのですが、こういう切り口での報道はほとんどなされていません。また、倒壊家屋の廃材の処理をリサイクル型でとの着眼点を持ち調査をするのは、復旧の邪魔をしにいく側面すらあって、新聞記者でさえカメラを構えることに抵抗があったといいます。全国各地から集まった多くのボランティアたちは、救援だけを前提に何か役に立ちたいという思いに駆られたのです。 私はたとえ一人ででも廃材への「虫の目」のつけどころを探しに行きたかったのですが、足の筋肉を切った後遺症に悩んでいて、交通の途絶した神戸を歩きまわるのを断念せざるをえませんでした。だから当初は市民研究員にも調査をしむけることをしなかったのですが、多くのメンバーがまさに自発的に救援に出動していてくれたことがわかった時、たいへん嬉しく思いました。 前記の課題への取組みを議論しはじめたのは、第2号が完成し、また現地の惨状も多少の落ち着きをみせてきた一昨年の秋頃からでした。 編集同人のIさんは、水洗便所が使えないとの報告は多いのに、水のリサイクルと切っても切れない関係にあるはずの下水処理についての情報がないので、この問題に挑戦したいと提案しました。これは正しい着眼です。 すでに大阪経済大の稲場教授が専門的な立場から某誌に投稿されていましたので、彼の指導も受けて市民としての見方を展開することをIさんにすすめました。取材の過程で、下水処理の原理を知っておきたいというIさんをやはり同人のB君が助けました。 そんな中、Iさんが私あてにくれた一通のハガキの次の一文が、私にとっては非常に印象深いものでした。それは、彼女が東灘の下水処理場を取材した直後の感想です。 「…とにかくたいへんな課題に取組みましたようで、ホトホト身のほど知らずに我ながらあきれ返っております…。」 ところが、この「身のほど知らず」ができねば市民研究員たりえません。本誌創刊号で、ナイアガラの滝下りに挑戦する「向こう見ず」のdaredevilを私が引用したのも同じ理由です。 専門の学者たちは必ず身のほどをわきまえて、原則的には他人の領分に手を出したりしません。ここに蛸壷ができる背景があります。また行政はそれを悪用して御用学者を育てます。 派手な開発優先と全国最低の福祉の神戸をつくりあげた共犯者は、オール与党の議会と職員組合、翼賛町内会、そして学者たちだと神戸大名誉教授の早川和男さんは指摘し、この総決算が震災だと書いています(※註1)。約150ある審議会に5つ以上も入っている教授が40人、そして20もやっている人までいるそうです。 私にも責任はあります。神戸の環境アセスメント審議会で矢継ぎ早に打ち出される六甲背山の大開発を止めることができませんでした。というのも、水質分科会に入れられた私は、大気問題に口を出せなかったのです。 ある時、公開されたアセスメント報告のうち大気の部分がおかしいと指摘する市民が、委員に会いたいと要求したのに拒否され、代わりに私が面会して意見を聞きました。なるほど山と谷の地形の設定法が間違っていました。市はアセスの理屈が正しい形になるように技術対策を挿入する《事なかれ主義》を貫きました。 こういう経緯もあって、「阪大で月給をもらって、仕事は神戸のためだけというな状況では責任が持てない」と私は辞表をたたきつけた次第です。 市民研究員のKさんたちの計算では、もし吹田の北工場で焼却すれば 90年もかかるほどの震災廃棄物が出たのですが、これも確かにリサイクルと大地震の接点です。 しかしそれ以上に、縦割り型で遮二無二(しゃにむに)中央突破してくる行政施策を横断型にワイドに受けとめて、政策提言に切り返してゆくボランティア活動にしか活路はないといえるでしょう。 ■市民参加の梯子 しかし個人が身のほど知らずだけで悦にいっていると、強固な組織はその足元を難なくすくうでしょう。したがって市民研究においては、そのネットワーク構成の善し悪しが今後の帰趨(きすう)を決めます。 千里リサイクルプラザの研究所長としての私のひとつの役割は、他のボランティア・グループにも所属して集めた情報で、研究所の血肉を豊かにしていくことです。下の図(図版1)は、今まで手当たり次第に入会してきたグループを整理してみたものです。もちろん20ばかりの専門学会にも入っていますが、こっちの方は重箱の隅の陳列が目にあまり、そろそろ脱会・整理にかかっています。手当たり次第とはいいましたが、レジャー型のものも計画的に加えていますのでご心配なく。 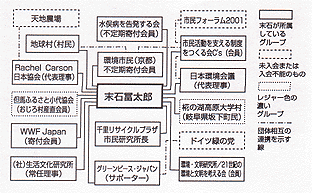 【図版1】 筆者が入会しているグループ図 このような前提で、私の秘書を務めてもらった堀田敦子さんが京都精華大学の大学院で修士論文を書くにあたって、テーマを「市民による環境ネットワーク構築にむけての一考察―廃棄物計画のなかの住民参加論をもとに」にしぼってもらいました。 その概要を別の角度から再構成して、研究所の『研究報告書』3巻1号に載せてありますからここでは繰返しませんが、チェイン・レター法(※註2)を使って、市民同士が環境についての情報交換や相互援助などの絆でつながっている模様を発見することが要点でした。堀田さんは、シェリー・アーンスティンによる「住民参加の梯子八段階」(図版2)を引用することから住民参加論を展開しました。 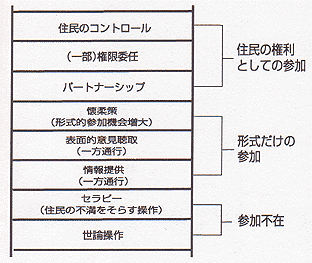 【図版2】 住民参加の梯子8段階(Sherry R.Arnestein,1969) この図には世論操作やセラピーなど、参加不在の段階も含まれていますが、震災後の阪神の復興計画でも一部の市民が納得したという、形式だけの市民参加の問題が何度も報道されました。これは、日常の公平性をほぼ達成した行政が、廃棄物処理や危機管理などある種の責任体制にかかわる問題については、市民に「知らしむべからず依らしむべき」という明治以来の体制を温存している証拠なのです。 これに対して図版3は、今度のホノルルの学会で最初に手にしたテキストで見つけた新しい梯子で、USEPAが1987年に書いたものです。参加不在の段階は消えてしまっていて、そして決定的なことをみつけました。最上段の「市民研究」です。 ただし、表現はCITIZENS MANDALAではなく、平凡なcitizens investigationでした。 しかし、だからといって、私たちは参加の梯子を一気にのぼりつめたわけではなく、今後も当分はもっと下の階段の参加方式にも経験を積んでいかねばなりません。その時問題になるのは、やはりネットワークのあり方です。神戸の救援ボランティアの総数が幾通りも公表されていますが、いずれもネットワーク性の不足が指摘されています。 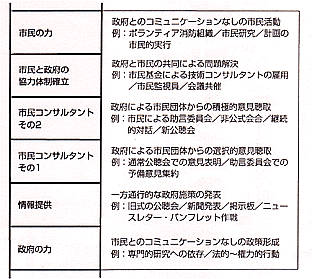 【図版3】 市民参加の梯子6段階(USEPA,1987) ■互聯網絡(ふーれんうゎんろー) 私が加入している団体のシーズ(C’s)は、市民活動団体を横断的に結束して、国に対して制度の改革を働きかけています。これと同じような団体でも、所属のメンバーが連携をとって活動しないと、せっかくのボランティアがいつも間にか純然たる「仲良しクラブ」になる恐れがあります。 堀田さんの京都調査では「環境市民」のメンバーが比較的多く紹介されました。私自身も「環境市民」を吹田の市民研究の有力な競争相手として位置づけていますので、表のすべての項目が総合されて「市民の総合力」が決まってくるはずです。 「環境市民」と吹田の市民研究制度は、ほとんど同じ時期(1992年)にスタートし、市の人口に対するメンバーの比率もよく似ています。私たちのほうが有利な点は、大学教員のコーディネーターをもっていることと、今はだいぶ窮屈になったとはいえ、財団基金の利息が研究に使えることで、だからこそ機関紙の発行も可能なのです。「環境市民」の活動費はすべて会員の年会費(5,000円)で賄われていますが、もしかするとこれがメンバーの意気込みの強さになっているかもわかりません。 「環境市民」も今年からマガジンを出す計画をしていますから、ここでも競争がはじまります。同じ目的でパソコン・ネットも立ち上げるそうなので、この点では吹田が一歩遅れをとっています。活動拠点を市内にもっと分散させるべきことは両方に共通の課題ですが、この種の拠点で親団体とまったく同じ活動をする必要はありません。工夫をこらした情報発信をすることが最初の目のつけどころでしょう。 外国人向けに大阪で開局したラジオ局『FM Co-Co-Lo』はこの好例です。 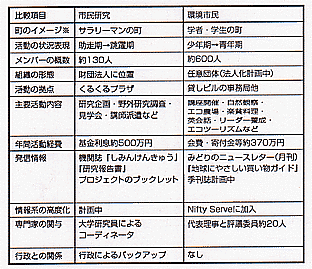 【図版4】 吹田の市民研究と「環境市民」の活動比較(※市民研究員F氏の表現) -------------------------------------------------------------------------------- 1995年11月12日26時に放映された読売テレビの「言いたい放題なにわのAPEC」という深夜番組に日本語の流暢なアジア人多数が出演、日本のいいところ、悪いところなどを意見交換した。また、この番組は10月16日に開局したFM Co-Co-Lo」(79・4MH)も紹介する。二つのCoはCooperationとCommunication、LoはLoveを表す。59人の外国人ボランティアがDJを担当し、震災関連などのニュースを14ヶ国語で放送していて、関西電力が資金援助しているという。辛辣さで有名な京大の高坂正尭さん(政治学/故人)が番組に助言出演していて、「こんなん知らんかったな、誰が考えたんや。脱帽や」と賛辞を惜しまなかった。 -------------------------------------------------------------------------------- さてパソコン・ネットの行き着く先はインターネットです。 -------------------------------------------------------------------------------- 前述のTV番組ではインターネットの中国語訳も紹介されました。それは「互聯網絡」といい、中国の留学生に「ふーれんうゎんろー」と発音することを習いました。 -------------------------------------------------------------------------------- 堀田さんが修士論文を書いている頃、全世界の加入者数は4,000万くらいだったのに、1年後にはもう8,000万に倍増したといわれているだけでなく、市民を意味するシチズン(citizen)のかわりにネティズン(netizen)という新語まで現れました。 このネティズンの特徴は、ラジオやTVのような拠点型・一方通行型ではなく、私たちが書き込み自由の回覧板を経路を問わずにまわせることなのです。これが21世紀型のコミュニケーションです。 ■ことば色の光 私はホノルルで観光行動を一切しませんでしたが、環境と観光を結びつける研究には手をそめていますので、何かひとつだけでいいからキーワードを発見したいと目を皿のようにしていました。 これだと合点したのが「ことば色の光」で、その象徴がほぼ毎夕見られる壮大な、しかも根元まで確認できる虹でした。観光とは光り輝く様を見ること・見せること、ことば色を7色と読めば、ハワイで交錯するのは現地語、英語、ピジョン英語、日本語、中国語、朝鮮語、タガログ語などです。 「環境市民」が京都ではじめたプロジェクトには、修学旅行生にエコ・ツーリズムを体験させる企画があり、この中にみやげ用の紙袋のリサイクルも含まれています。大風呂敷を広げれば、リサイクルで吹田を光り輝かすこと、これが市民研究を手段とした目的だといえるでしょう。 *註1:大学基準協会(Japanese University Accreditation Association )の機関紙「JUAA No.14,1995」より *註2:チェイン・レター法/「幸福の手紙」のように、最初の発信と同じ内容の手紙を逐次受信者の知己に送ってもらうよう依頼して、情報伝達の和を次第に広げていく方式。ここでは、調査者がボランティア活動に関するアンケートをする必要上、各ステップごとに受信者にいちいち知己を紹介してもらい、手紙の発信者は常に調査者が行うようにした。 |