| ■市民研究宣言 Ⅳ 1998年3月 千里リサイクルプラザ研究所 機関紙『しみんけんきゅう』第4号 プラザの5周年特集と銘打ったこの号が出版される頃には、吹田の市民研究員制度ができて約6年になる。私を含め、初期の主担研究員の井上・土屋・吉村の4人が大学研究会の名前で、市の事務局員といっしょに手弁当で(いや最初は弁当もなかった)、あらゆる想定局面について予備検討をした期間も加えると、もう10年近くも経過したことになる。 この間、陰に陽に研究所の充実のためにご支援を賜った関係各位と、自発的にしかもほとんど無償の活動に取り組んで下さった研究員各位に、厚く御礼を申し述べたい。 しかし、私の独断かもしれないが、研究所がたどりつくべき目標は、まだはるか遠くにある。ゆくゆくは市民みずからの「政策接言」をといい続けてきたが、正直にいって、現在の地方行政の代替を果たせそうな気配は全くない。現在は明治維新や敗戦時に匹敵する大変革のチャンスだといわれてはいるものの、私たちが囲い込まれその中で安住してきた「箱」から出る勇気(中山素平)(※註1)はまだなく、また「気骨ある異端」を抜擢する社会的素地(城山三郎)(※註2)もできていない。 私はこのシリーズの123で、直接には市民研究員への激励の意味を込め、上のようなメッセージを発信してきたのだが、今回は同じことをやや辛口で述べたい。5周年に免じて容赦頂きたい。 ■お山の大将か、真のリーダーか? この4月から、滋賀県立大学環境科学部の環境社会計画専攻は、富山高専で電気工学を専攻していたブラジル日系二世のアネガワ君を、最初の編入学生として迎える。彼はもちろん入試を抜群の成績で突破したが、専攻を180度変更する理由づけも堂に入っていた。 その彼が昨年末、下宿探しの途次大学に立ち寄り私を訪ねてくれた。専攻転換のハンデを克服してあと3年かかってでも卒業をし、大学院へも行くという。 末「それから後の計画は?」 ア「日本のどこかに環境の大学をつくりたい、しかしやはりアフリカが一番いいと思います。」 末「(ウーム、いうなぁ!)で、具体的な計画は?」 ア「それはここでしっかり勉強してからですが、もう文部省には手紙を書きましたよ。」 末「ウーン、素晴らしい。多分文部省は返事をくれんだろうが、まだ生きておれば僕は君の応援を必ずするよ。」 私にこういわせる日本人学生が、今私たちの周囲にいるだろうか?これが第1の問題。大学の就職課は今年あと僅かで切って落とされる第1期卒業生の高い就社率を実現すべく、私たち教員にも企業訪問の重圧をかけてくる。つまり既存の「箱」への詰め込み作戦に徹している。これが第2の問題である。 しかし学部の就職委員長もしている私が、少人数の学生相手の時は、「吹田の市民研究員にはあえて就職をせず、フリーターしながら研究所の仕事を分担してくれている人もいるよ」と吹聴し、「諾君には先輩はいないが、私の門下で世界の経験をもっているのは100人を下らない、日本国内では1,000人はいるから心配するな」といっても、誰も質問にも来ない。これが第3の問題だ。 フリーターは所詮アマだから、厳しい日本社会の将来運営をアマに任せることはできない。何っ?市民研究員もアマだって。そう、今はそうだ。しかし市民研究員がプロ的になり、国の経済規模の中で、一定率の雇用と所得を確保するようになるとどんなことが起こるか。私ひとりでは手に負えない仕事が上の3つの問題から見えてくる。 それは、現在の市民研究員たちがみずからリーダーとなって、次世代の市民研究をになうべき若者を、「環境社会」を標榜する分野からリクルートしてくることである。滋賀県大に限らない。2001年開学予定の(仮称)鳥取環境大学(公設民営)にも、「総合的に勘案して」という甘ったるい表現の「社会環境学科」を設けるという。こういう大学に求人の先制パンチを喰らわすような方法を、わが研究所も工夫しておくべきなのだ。 私は昨秋ある講演の聴講に東京神宮前の国連大学へ行き、ついでに学内で種々の資料を展示している地球環境パートナーシッププラザに寄った。資料は主として環境庁経由で集められていて、わがプラザの情報資料コーナーにあるような各都市の資料がぎっしり並んでいた。ところが吹田市のファイルはどこにもない。つまり、環境庁には私たちは認知されてないということか。リサイクル分野に限れば、5周年事業のように全国から参加者を集められるけれど、世界的視野でみれば、吹田はまだ「お山の大将」なのではなかろうか。 前兆がすでに見えだしたように、至る所で「市民研究」の真似事が始まって、大学も「環境、環境」と大合唱をすると、「箱」は大きくなっても中身はお遊び、と酷評されてしまうだろう。箱のすぐ外側には、女性や人権の問題も溢れている。 ■温暖化防止京都会議の結末 京都のCOP3に長期間全力投球した学生たちやNGOには気の毒だが、この会議は一体何だったのか。私たちの5周年事業がこれに重ならなくてよかった、と思えるほど、マスコミは約1ケ月間、%の数字で喧噪をきわめた。 COP3直前の講演会で「温暖化は科学者が解決するのだ」と獅子吼した人もいたが会議での出番はなく、単純すぎる(洋上に浮かぶ白雲の効果など、結果をどちらに向けるかわからないサブモデルを含んでいないこと)温暖化モデルに批判的な学者は、一歩距離をおいて眺めていて、超複雑な地球の機序は、いかに大型計算機を並べても、普通の科学で解けるわけがない(本号の小松左京の論文も同じ立場を表明している)。 しかしわが研究所もNPO/NGOには違いないから、会議場の雰囲気だけは味わってもらいたかった。COP3に限らず専門家の間では、重箱の隅をつつくタイプ、大型予算や大規模施設に依存した力任せの研究が繁盛していて、専門バカの様子も観察できる。また一方では自分の意見で相手を説得するコツを盗みとることもできる。このために、私は徐々にではあるが、「市民も歓迎」という学会を覗くことや、外部への講師役の機会も提供してきたつもりだ。 TV報道で目立ったのは、グリーンピース・ジャパンの松本泰子さんと、気侯フォーラム代表の浅岡美恵さんだった。二人ともいわばロビイストとして、日本やアメリカの代表に炭酸ガス削減率をもっと高められる根拠を示して圧力をかける仕事で奮闘していた。この根拠とは、必ずしも「科学的」なものではなく、省エネ・省資源の生活スタイルが基礎になる。 しかし少なくとも日本政府の原案は、この根拠を一切公表せず、最終的には力関係と妥協の産物として、国別の削減%数字を近づけあったのだ。 やはり本会議の直前にボンで開かれた予備会議に日本代表は、炭酸ガスを出さない発電を、として原発政策の推進を提案したが、総スカンを受けて即座に白紙撤回した。しかし国内では依然推進方針に変わりはない。これに比べてアメリカは相当柔軟である。COP3とほぼ平行してエネルギー庁は、世界8カ国の代表を集めて原発終止の作戦会議を開き、ここへ日本の「環境総合研究所」副所長の池田こみちさんが招聘された、というニュースが私のところへ入ってきた。この研究所は株式会社形式のNGOである。 浅岡さんの本職は弁護士だが、京都の「環境市民」の代表でもある。プラザにもお馴染みの事務局長杦本育生氏から昨夏、私はCOP3への協力を依頼され、適宜市民研究員を派遣する旨快諾をしたのだが、やはりリサイクルだけでは役不足だったのだろう。 ■NPO/NGOの日米比較 以上に述べたことの裏面には、もっと多くの複雑な事情が隠れているはずだが、「虫の目」で見つけた兆候のかげでさらに大きな潮流が動き始めている、と仮説すると、次のことがいえると思う。もちろんプラザまたは研究所が、「箱」から出ることを前提にしてである。 ①リサイクルよりも温暖化問題のほうが大事だとはいわないが、両者の共通項としての生活スタイルを市民側から提案すること。その評価基準は、エネルギー削減であること。だからリサイクルに余分のエネルギーが要る場合は妥当性を欠く。 ②民事・刑事事件の被告の代弁をしてきた弁護士の仕事が、環境の代弁役にも広がっていること。このことは、私たち主担研究員も意識している。 ③現在の政策決定者は、国連も含めて、表面上は科学の成果を利用しているようにみえるが、それは科学者の懐柔であったり、形式的な意見聴取にすぎないこと(これは、本誌第3号の拙稿の【市民参加の梯子】の図と相似である)。 ④COP3との直接関係はやや弱いが、市民側の政策提言の介添えができるのはやはりマスコミであり、彼らの注目を惹く言語表現能力が必要なこと。 ①②③④のすべてが、現在の私たちの市民研究に埋め込まれていることは間違いないが、残念ながら、まだすべてが有機的につながっているとはいえない。 一方私は、最近NPO/NGOのリーダー養成講座が増えてきたことに気づいたので、別の研究所で総合研究開発機構の助成を受け、その実態調査を始めた。昨年12月アメリカ総領事館で受けた講義(デボラ・マグローフリン)(※註3)でいくつかの重要な事柄を発見した。それらをまとめると、右の①②③④との関係がよくわかるのである。 (1)アメリカの経済規模は、一人当たりでは日本より低いが、NGO寄与分が雇用で11%、所得で7%もあること。 (2)弁護士の仕事を表現するアドヴォカシーという用語が「政策提言」と訳されたこと。 (3)NPO/NGOの経費のうち、フォードやマッカサーなど大型財団や企業の慈善的寄付による分は多くなく、各種講座の参加費収入が軸になっていて、しかも小さなNPOでも新しい市民活動の助成に主眼をおいていること。 (4)市民養成の中心機能は、学生を連れた大学教授たちがシンク・タンクに自由に出入りして分担していること。 (5)日米共通の欠点は、リーダーたるべき人が多忙すぎて戦略を練る時問がないこと。 ■今後の5年に向けての課題 次は10周年事業だ、という軽々しい目標設定は明らかに不適当である。私の観察結果では、5周年事業に集まって下さった各地のグループの中には、先ほどいった「箱」の中の真似事とおぼしきものが少なからずあった。もしこれらの組織が「市民研究」を使いだすと、先端を行っているわが研究所の神髄を理解できないひ弱なマスコミが、レベルは低いが人数が多い集団を「贋もの」と見抜けないで、「市民研究」のお墨付きを横流ししてしまうのである。こういう苦い経験を私はこれまで何度も味わっている。1980年に阪大の末石研(盛岡・日下・八木)が開発した環境家計簿はその後2年ほど引用されただけで、最近突然低次元のものがもてはやされているのである。 そこでここで宣言しておきたいのは、①②③④(1)(2)(3)(4)(5)の大部分の意味が理解されておらず、努力の痕跡もみえず、単にボランティア性だけが喧伝されているグループとの平凡な交流を絶とうではないか、ということである。 日米比較の項目からはあえて外したが、日米ともNPO/NGO間のネットワーキングの方法は未確立だ、とデボラさんは述べた。普通なら、これをうまくこなしてくれるのがインターネットだという前提で、あえて無用のところとの交流を絶つには、それなりの見識が必要である。 例えば日本の国際交流は、永らく「国際直流だ」と外国から陰口をたたかれた。年間1,700万人近くが外国旅行する時代になっても、土産の仕込みにうつつを抜かす限り、本当の交流(exchange)にはなりえない。 そこで結論はこうなる。5周年の企画段階と反省段階で、多く出た意見は、市民研究員や工房指導員への権限委譲であった。(5)のためにも私は大賛成である。しかし「箱」の枠組みを変えなければ、贋物と肩を並べてしまう危険性が多い。 権限委譲を分担してくれる人には、箱から出て、「分散研究所」や「分散工房」を創って頂きたい。現在のプラザはもっとシンク・タンク機能に重点を移し、かつ基礎講座を養成講座化して、その収入相当額を分散機能への助成にまわす。もちろん一歩水をあけられた観のある「環境市民」がメンバーの納入する会費だけで動いていることも参考にすべきで、この自発性こそがボランティアの本旨であるし、アメリカ経済が再活性化した理由でもあることを忘れてはなるまい。以上のイメージは、『研究報告書』第1巻に既に表で示しておいた。それをここに再掲しておく。表の内容をもっと充実できることはいうまでもない。 こういう成果が少しでも現れることを期待して、『しみんけんきゅう』次々号を英語版の“CITIZENS MANDALA”にすれば、3年前に研究員のY・S氏が提案してくれた国際交流に本格的に挑戦できるようになるだろう。 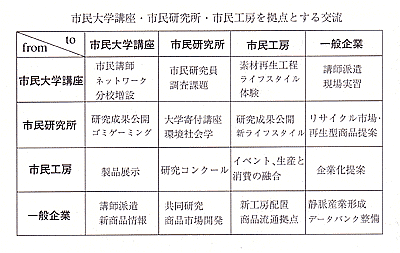 ※註1中山素平:1906年生まれ。昭和期の財界のリーダー・銀行家。東京商科大(現・一橋大学)卒。 日本興業銀行へ入り、41才で理事。GHQの興銀解体を条理を尽くして中止させ、長期信用銀行への転換に努力し、61年に頭取。日本開発銀行理事を務める。アラブ湾岸諸国を歴訪し、プロ養成を目的に、国際大学を設立し、理事長となった。 ※註2:城山三郎:1927年生まれ。東京商科大(現・一橋大学)理論経済学卒。小説家。 57年『輸出』で第4回文学界新人賞受賞。58年『総会屋錦城』で第40回直木賞受賞。以降、企業の内幕とそこに展開する人間模様を描いた経済小説を書き続け、今日の企業小説の先駆となる。96年に、伝記文学に新境地を拓いた功績により、菊池寛賞を受賞。 ※註3 Deborah McGlauflin :Connecticut大卒、日本女子大大学院、Hawaii大(東アジア研究/修士)を経て、難民・開発・市民革新などのNGOで企画・資金調達・事業管理を20年問経験、現在Insight-in-Action社社長(40才代後半と見受けた)。 Advocacy:弁護、擁護、唱道、鼓吹(研究社英和辞書)。鼓吹には[urge by argument]の説明があるから、これが政策提言とつながるようだ。滋賀県大の私の専攻は、環境mediator(仲介人・調停者)を養成することを公言している。mediatorには日本の労使調停とは違って、2頭以上の荒馬を乗りこなす能力が要る。末石は、Pennsylvania大学に環境mediatorの養成機関が15年前にできたこと、California州庁には、都市問題や海岸保全部門に独立職能をもつmediatorがいることを知っていたので、デボラになぜmediationを講義で一切使わなかったかを質問した。彼女は日本語も堪能だといった上で、「言葉を慎重に選んだ。advocacyにもっと大きな意味をもたせたかった。よく相手の話を聞くこと、市民の力が政治より上にくるようなmessageを打ち出して外交手腕とbridgingする、誰の支援が要るかまたtargetは誰かを見極めることなどが含まれる」と答えた。こういう説明と比べると、日本の場合は、まず安穏な合意形成が第一になっていて、さらに「議事進行」の掛け声や時には灰皿が飛んだりする。 |