| ■市民研究宣言 Ⅴ 2001年10月 千里リサイクルプラザ研究所 機関紙『しみんけんきゅう』第5号 私の巻頭エッセイはこの号で終わりにする。もし次の担当者に引き継ぐとしても、「宣言」という表現は改めねばなるまい。 行政一般で使われる言葉を参考にすると、「非核都市宣言」のような憲章がこれに相当する。非核都市の現代的意味はいささかも古びていないが、仮に吹田市のこの宣言にネガティブに作用する力が現れたとして、果たしてわれわれはこれに対抗できる手段をもっているか、と問えば、かなり心許ない。周辺有事立法の定めでは、神戸のような一般港にさえ原子力空母が入港して、後方支援資材の調達をすることが含まれているのである。警えは適切さを欠くが、環境先進国と称されるドイツがバーゼル条約に反する世界最大の有害ごみ輸出国だ、という事実を隠すわけにはいかないのである。 市民研究の前段階には「市民運動→学習」がある。「宣言Ⅲ」の【図版3】に描いたように、結果的に吹田の市民研究は、市民参加の梯子の最上段に強行着陸したので、正直にいって、「運動→学習」の経験豊富な猛者だけが切りまわしているとはいえない。直裁的な答えは運動への再回帰である。でもそれは幟(のぼり)を立てたデモ的な運動ではない。市民の政策提言を含む一連の行動である。そしてこの行動に、これまでの研究成果が反映されるべきことはいうまでもない。 ■日本の窮状―前門の虎・後門の狼 一難去ってまた一難と言い換えてもいいが状況はもっと悪い。〝Between the devil and the deep sea〟のほうが適切だ。非核都市の前門にはオルブライトのようなdevil然の人物を擁するアメリカがいて、後門には日本の進路に疑念をもつアジアという深海がある。沖縄サミットはアジアの反先進国のNGOに包囲されるという動きもあった。この日本を率いているのが「どこに出しても恥ずかしい」森 喜朗なのである。 筑紫哲也の分析は、総選挙前にあれほどコケにされた若者の無党派層はすでに日本の将来に匙を投げていて、これを背景とした英語ブームがあり、アメリカで通用する資格をとって日本脱出を目指しているのではないか、という。中年以上の大人は、まさかそんなことが起こるものか、と筑紫の分析を一蹴するだろう。しかしそれは甘い。彼の国際経験と比べて、われわれは去年も今年もそして多分来年も変わるまい、と思いがち、例えばそごうの救済のため多額の税金が投入されそうだと聞いても、子供のため払ってきた教育費の見返り、未完済の住宅ローン、不安定な老後設計、などに気をとられて、反乱に立ち上がる発想も勇気もない。アメリカの経済学者ハーシュマンは〝voice or escape〟といい、パワーを含むボイスが行使できねば脱出しかないといった。もう20年も前のことである。 若者世代の約半数が在籍する大学で、多数の学生は概してまじめに、少々下手な講義にも我慢して単位を取り、即戦力を求める企業に就職していく。しかし、卒業や就職を度外視する学生も相当いて、正規のルートと無関係な実に多様な企画を次々に打ち上げる。例えば「このままでいいのか?県立大学」と銘打った催しは、教員と学生のパネル討論を盛り上げたが、別に斬新な結論が出るわけでなく、実施したことにだけ価値があるという具合だ。残念ながら、これらの企画はほとんど平凡な世間の情報に誘導されたもので、目的達成の準備研究が不足、そのためにこそ身を入れた学習が欠かせないことに気づいていない。しかしとにかく、これらのグループ間にネットワーク化の楔(くさび)を打ち込めば、これが思いも寄らぬ後門の狼となって、大学の存立基盤をゆるがすであろう。前門の虎はいうまでもなく、すでに政治日程に上がっている独立行政法人化である。 ■直接民主主義の光と影 誰が何と言おうと、この混迷をきわめる日本社会で、最終針路の決定は市民集団の手に委ねられるべき、とする意見は日増しに高まっている。もちろん、住民投票結果では市民側の意見が大勝を博しても、議会がいとも簡単に否決したという事例には事欠かない。神戸空港の計画反対の投票は成功したが、白分たちの税金が使われることには無関心、「やっぱり空港はあったほうがいいのにねぇー」という市民がなお多数を占めている。そのためかどうか、投票結果を議会が否決した後の笹山市長のリコール運動の矛先は鈍ってしまった。この場合でも、関西新空港の候補地が泉州沖に決まる前に、神戸市は神戸沖案を拒否していた事実はほとんど忘れ去られているようだ。マスコミにもその記憶すらないようである。 四国吉野川の第十堰(徳島市)改築問題は、一歩前進した。市議会が投票結果に同調したからである。しかし中山前建設相に「民主主義の誤作動」と言わせ、これが、小渕前首相の病状秘匿や森内閣立ち上げの不審、その後の森去言の多発とひとからげにされて、不穏当だという糾弾に曝された。 私には中山正暉を擁護する義理は一切ないし、また「誤作動」は多分建設官僚の入れ知恵に違いないとは思うものの、住民側も誤作動の禁を知らぬうちに犯していると見た。建設省にはまだ隠している情報があるという前提でだが、住民側は「150年に一回の洪水で」というキーワードに対して妥当な反応に成功していないのである。彼らは、いったん計画を立てたら遮二無二実行するこれまでの公共事業の性癖に突き動かされていることは間違いない。1752年におそらく農民たちの献身で建設されたこの堰は、以来いかなる維持策が投入されたのか、それを将来の吉野川計画にどう反映すべきか、の展望を述べえてはいない。 多数決の非を説く数学ゲームにこんな例題がある。厚さ0.1ミリの紙を100回折りたたむと、最終の厚さ(高さ)はいくらか?東京タワー(330メートル)、富士山(3772メートル)、東京~大阪の距離(550キロ)、太陽までの距離(1億5千万キロ)、宇宙の果て(9.4×【10の21乗】キロ)、の5肢のひとつに直感で投票せよ。 正解は宇宙の果てなのだが、投票結果では常に【東京~大阪】の中庸値が選ばれるのである。つまり、間接であれ直接であれ、民主主義が誤作動するのである。これを回避するには、正しい計算法を知って互いに意見交換した後に最も妥当な答えを出すという手続きが必要なのだ。 ■上越市副市長事件の意味するもの 上の練習問題は非常にうまくできているが、多くの社会問題一般、わけても合意形成問題は、もっともっと複雑怪奇、私にいわせると、複雑系を通り越して困惑系でさえある。その典型がごみ問題だ、といえるのだが、大部分の人はまさかと軽視する。このまさかまさかの隙間に、暴力団の資金源や生賛を血祭りに挙げる責任回避行動が忍び込む。みかけはもっともらしいものもあるだろうが、図に示すように、日本のごみ焼却単価は諸外国に比べてなぜ2倍近くもかかるのか。しかもこの原資には、国会審議も経ないで閣議決定だけの財政投融資資金(郵便貯金などを運用、2000年度で終わる第8次廃棄物処理計画は、総額5兆500億円)を投下したのである。 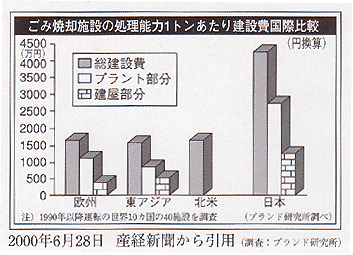 何をいまさら、品目別リサイクル法だの、循環杜会立法など、上っすべりの法律などは要るものか。私個人は、すでに1967年の「清掃事業近代化」の全国規模の研究で循環社会を提案したのだが、結果は「全国都市清掃協議会」の大圧力に押しつぶされて、全量焼却へひた走る旗振り役をする羽目になった。 こういう歴史の中、上越市が三菱総研の支援をえて、人口13.5万から30万への発展を謳い、環境部門の副市長を1999年5月に公募、同年7月から、資源循環型社会の形成などのリーダー役を応募者約100人から選んだ高畑佳壽子に託したのである。高畑は主として環境税の導入を軸とする政策を提案したのだが、結果は無残、わずか1年後の6月23日付け朝日新聞の記事は、「市民提案に厚い壁」という大きな見出しを掲げ、市長が高畑提案を時期尚早として却下したと報じた。しかしその背景には彼女に対するセクハラもあって、結局、依願退職が馘首になってしまったのだ。 これではまさに、市長の身代わりの生賛になるために副市長に就任したようなもの、でも市長の背中にも、焼却量が減っては困る業界の匕首が向けられていたかもしれず、とても一人の副市長に対処できる課題ではなかったのだ。でも、日本に千人はいる環境税の学者たちは全くの音なしだった。 ■新世紀のリーダーへの期待 いま日本のリーダーとしての人気が高いのは誰か。永田町内では田中真紀子が一位だが、でも支持者は15%くらい、東京都の石原慎太郎がダントツである。石原は1973年7月に結成された自民党若手のタカ派集団「青嵐会」(中尾栄一や森 喜朗、ハマコーこと浜田幸一ら31人が所属)の幹事長をしていた。その体臭はいまも褪せてはいない。前の知事選では、青島幸男の引退の後を受けた明石 康、岩国哲人、舛添要一、三角 寛らひと癖もふた癖もある候補者が競り合っているとみるや、告示日ギリギリに立侯補を表明して漁夫の利をさらったのである。そして、銀行に対する外形標準課税で都民の喝釆をえるリーダーの手口は、果断ではあるがナショナリズム型の典型と評されている。 私が忘れられないのは、彼が環境庁長官時代に強引に押し進めた、窒素酸化物にかかる大気環境基準の緩和である。1970年の公害国会で与野党が一致して決めた、公害対策基本法の「経済と環境の調和」条項の削除を彼は強く批判(77年秋)し、調和復活に動き始めていた産業界をリードすることになる。 私自身にもそういう立場の論文を書けという要請が再三きた。全力投球したのは「石原慎太郎の功罪」という小見出しも含んだ「経済と環境が調和する時―新しい科学の萌芽をめぐって」(『経済評論』27巻6号、78年6月)である。 この論文で私は、石原が庶民の思考の埒外にあるヨット生活を誇らしげに語ってみせ、その一方で、真夏にクーラーが止まった生活を現代人は文化的と呼びはすまい、といって、トレードオフの支点を混乱させ、それまで窒素酸化物の環境基準値0.02ppmの根拠となっていた疫学データの「非」科学性をなで斬りし、この厳格な基準が性能のよい自動車の過剰輸出につながっているという欧米の圧力にはことさら触れることなく(『ノーと言える日本』はおくびにも出さず)、基準緩和発表の日にロンドン・サミットに出ていた福田赳夫首相が満面の笑みを見せるまでの見えにくい筋書きを解明した。つまり、もし将来調和が達成されたとしても、その時の経済の姿は完全に変わっていることを力説したのである。 結論を急ごう。期待されるリーダー像は、森でも石原でも田中の姿・形にも求められない。明らかにもっと小集団の中で、リーダーとフォロワーを相互に交代しながら、誤作動をせぬよう合意形成を誘導できるメディエータ(mediator=橋渡し役)の形式が妥当しよう。さらに追加すれば、市民研究からえられた政策提言は、市長、議会、役所宛てはなく、この形式の濫觴(らんしょう)である市民集団じたいに向けられるべきである。だからこそ市民研究の拠点をもっと分散させねばならない。本号の別稿で報告したように、中坊公平弁護士の指導原理も豊島の住民に向けられたものだったことに留意しよう。 ■人之将レ死其言也善 人のまさに死せんとする、その言や善し。この「人」とは私のことである。西丸震哉の『41才寿命説―死神が快楽社会を抱きしめ出した』(情報センター出版局、1990年)を参考にすると、私の世代は去年までに半数が死亡していることになり、大学の同級生を数えてみても西丸説はほぼ妥当である。こういう前提で私の言い分を読んで頂こう。悪いことを隠して善いことばかりを言うわけではない。この世に真実などがあるとは思わないが、真贋を見抜くことの重要性を問いかけたいのである。 応募者の資格を一切問わない市民研究員の方たちと交流するうちに、大学では教育し易い学生を集めるために入学試験をしているのだな、ということに私は気づいた。それでも入試改革のつど試験内容は志願者に迎合的になってきたし、偏差値がかなり高いとされる滋賀県立大学でも、学生の茶髪はザラだし、ガングロに超ミニスカなども珍しくはない。 最初にも述べたように、現在の大学ではまだ小・中校のような学級崩壊は起きてはいないが、前途にはより解きにくい困惑の渦中に陥る予感がある。こういう中で、従来と同じ学部・学科編成と、所属教員の2単位ずつのコマ切れ科目を学年別/必修/選択で飾ったカリキュラムを麗々しく学則に載せるやり方は、教育組織の無謬性を偽証しているのではないか、と私は思うようになった。私がもっと若ければ、こういう発言は口が裂けてもしないだろう。しかし、まさに誤作動の極から出てきたリーダーを戴いて、嘘や密約や情報隠しの海を泳がされる生活にはもう飽きあきした。塩野七生は「職業にはなくても、生き方には貴賎がある」という。大学教授の権威で講義の真実性を押し売りする生き方は、賎しいとはいわないまでも、かなり貧しい感じである。 滋賀県立大学環境科学部でいま評判のよい方式は、内湖の強引な干拓など県の失政の結果、難題が住民にしわ寄せされている地区の継続的な「環境フィールドワーク」で、学生と地元住民の交流を教員が支援しながら解決策を模索しようとする科目と、当初は0単位で始めた少人数クラスの「表現演習」である。これらは、市民研究スタイルとの類似点が非常に多い。空洞化した彦根の中心市街に開店したACT(Action Connect with Town)ステーションでは、教員が顧問団になってはいるが、自主的な運営は複数の学生に任されていて、彼らは卒業を第一条件にはしていない。関学大の街角ラボ(三田市)もほとんど同じ試みだ。 先ほど私は、市民研究の強行着陸という表現を使った。もし軟着陸地点を探すとして最大の課題になるのは、市民研究員に要求される一種の資格要件である。もし10年前にこの手の議論を始めていたら、甲論乙駁、結論はいっも先送りになって、いまもって市民研究制度は立ち上がっていなかったであろう。30年近くも全量焼却以外に目を向けなかった日本の廃棄物行政を、あえて失敗の連続と位置づけると、この方向転換をはかる主力は市民パワーをもってする以外にない。このことはすでに、『研究報告書』の第1巻にも詳述してある。 これでもう、言い残すことは何もない。あとは、吹田市民個々に生活態度の貴賎を反省してもらうだけ、最大の敵は「わたし一人くらい・・・・・・」という甘えである。 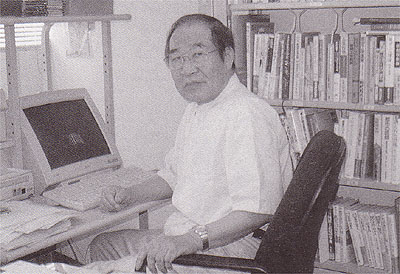 滋賀県立大学研究室にて |